京都の名門企業である島津製作所。最近では創業150周年の記念アニメーションを公式から出されています。
📒 Summary + Notes | まとめノート
京都
京都は長い歴史がありますが、1868年ごろ江戸から東京へと名称が変わったところは天皇の即位の礼があり京都御所から天皇が移動しました。当時、京都の人には1870年には還幸すると言われていましたが結果帰ってこない、事実上の首都移転が起きます。
この影響により公家が東京へと移転し、公家屋敷は廃墟になり、商売でも虎屋などを代表に東京へと人々が移動していきました。35万人いた人口が20万人まで激減。
その荒れた京都にて再建の活動が行われます。その指揮を取ったのが槇村正直であり京都の街の整備、改革が行われていきます。そこの波に乗ったのが島津製作所の創業者島津源蔵です。
元々は仏具の販売をしていましたが廃仏毀釈により仏具や寺が衰退し事業転換を試みていました。理化学機器の発売を始め科学技術へと舵を切っていきます。
現在の西本願寺の近くは今でも仏具商が残る地域ですが江戸時代後期にも31の仏具商が居たという記録があります。1868年に時代が明治に変わろうとしたことには神仏分離令が出され、仏と神を明確に切り分け仏教から神道への道へとの転換を国がはかります。
今も大きな土地を持つ京都の寺ですが、高台寺は約1/8の面積に、清水寺も15万坪から1万坪へ、東本願寺は4万坪から1万坪へなど召し上げられる形となります。
仏具商としては苦難の時代にあり、仏具を作成していた島津源蔵は経営も厳しく、また今でも残っている島津源蔵作の仏具は千本ゑんま堂に残るぐらいだそうです。
槇村正直と同じく京都の再建で活躍したのは山本覚馬です。後の同志社大学創設者でもあります。
島津源蔵
島津源蔵は高瀬川の源流部分にて邸宅を持ち、舎密局にて出入りすることから科学技術の勉強を見様見真似で行います。出入りをする中でオランダ人のヘールツなどとの交流も重ねることができ、理化学機器の製造を始めます。
ヘールツが舎密局を去った後にはドイツ人のワグネルが恩師となります。有田焼の釉薬や釜の改良を行った人物であり、科学技術の知見を多く持っていました。
気球の打ち上げ成功
150周年記念ムービーであるように気球の打ち上げに成功したことは島津源蔵の名を大きく轟かせるでき事でした。当時ライト兄弟が1903年に飛行に成功したのですが、このイベントは1877年であり空に浮かぶという事がどれだけ不思議でありすごいことであったのかイメージできます。
京都の科学技術のアピールのために京都独自の博覧会が京都御所で行われました。同年は西南戦争が起こるような混乱の時代に京都は新しい路線へと向かう事を市民にも宣伝する理由もありました。
弾力性がありつつもガス漏れを防ぐ必要がある気球素材が課題であり、木綿の布に油やにわかなどを塗り改良を重ねます。京都府は鑑賞券を売り出し米一升が5銭であった時代に3銭の一般料金であり学校の教師や生徒はその半額で販売、券は完売し府は予想以上の収益を上げることになり「明治考節録」の本を出版し各学校に配布することができました。
気球や理化学機器などについて島津源蔵は「なぜ日本人はできないのか?」と思い西洋の科学技術を学ぶべく小さい頃から西洋書物を読み込みました。1884年には京都の都をどりを電灯で照らすという当時では革命的な取り組みをサポート。イギリス人技師が主にやっていたところ体調を崩して数日休まなければいけなかったもののそれまでの会期中に原理を理解した源蔵は問題なくこなし、芸姑、舞妓さんがどんな仕組みになってるか彼に訪ねてくるほどでした。
二代目源蔵
源蔵の息子であった梅次郎は奈良の女性であるつると縁談により結婚。26歳の頃には55歳になった一代目源蔵が亡くなり梅次郎が源蔵の名を継ぎます。
島津製作所の名を広めた気球の打ち上げでしたが、二代目源蔵も島津製作所を大きく拡大していきます。その一つのきっかけとなったのは現GSユアサの社名にあるようにGenzo Shimazuによる蓄電池です。本書を読んで知ったのですが島津製作所は様々な会社の源流にあたる会社であり分社化した企業が様々あります。
1892年に京都で電力の供給申請が済まされ京都電燈が電力サービスを始めます。ただし当時の電力供給は安定せず、工場の電力を賄うには頼りないものにありました。そのため蓄電池技術を開発し自社で使用する必要性に駆られました。
技術を身につけるために西洋書物を読み、京都帝国大学に理工科が新設されたために最新の学問を学びに出入りし始めます。教授も協力します。教授から実習用の蓄電池作成を依頼されると、京都帝国大学内にあった古い蓄電池の分解から構造を理解し完成させてしまいます。
当時日本で蓄電池を作成できる工場はなかったために同技術を持って生産することが日本の技術革新にとって重要な課題となり1903年に今では結婚式場として使われている市役所裏の土地に工場を構え蓄電池の製造を開始しました。1904年には日露戦争じに無線の電力源として戦争勝利につながる蓄電池を供給。これらは工場の稼働のために設置してあったものを急務とあって取り外し戦争用にカスタマイズしたものでありました。
驚くことに1925年ごろにはアメリカからデトロイト号と呼ばれる自動車が輸入されていたためにそれを改造して電気自動車として利用。当時の市電が30キロほどの速度しかないところ60キロもの速さで走行可能でした。
戦争とその後
戦争が終わるとGHQの監督のもと日本の整備が始まり、島津製作所も自宅邸は一部を残して回収されるなど行われます。戦前に話が戻りますが、島津源蔵の息子である島津良蔵は芸術分野、ファッション分野で活躍し、日本中にあるマネキンは島津製作所で作成されていました。のちに分社化した七彩という会社は現ワコールホールディングスの傘下に入っています。戦時中にマネキン製造は中断し社員が徴兵にあいとても存続できる状態にありませんでしたが、戦争が終わり生き延びた社員達はまた戻って来るとマネキン事業も大きく伸びていきました。
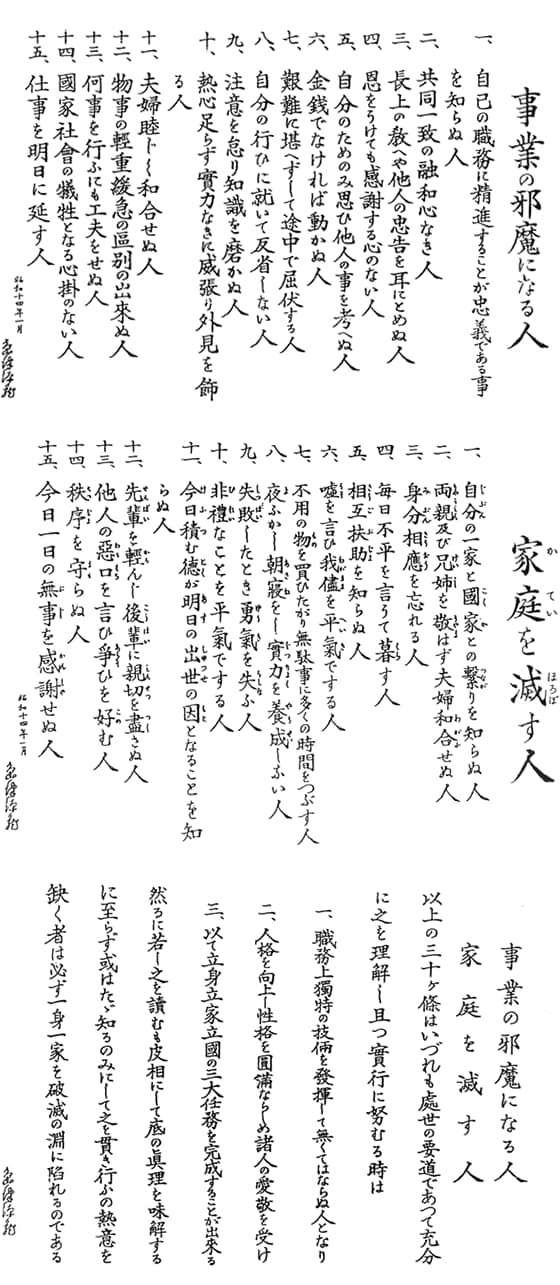
引用:https://www.shimadzu.co.jp/aboutus/company/history-gz15.html
感想
ソニーやホンダと比べると地味な存在である島津製作所ですが、GSユアサなどを代表に現代風に言うと連続起業家であり、明治時代からの科学技術発展をいち早く実践した存在ということに驚きでした。
桜の季節の京都を楽しもうと思い新幹線の中で本書を読んでいたのですが、京都についた後に観光の最初に島津製作所の発祥の地である高瀬川の源流付近を散歩しました。
想像すると、江戸時代の終わりごろに革命的に新しい政権が誕生し元々京都に居たことが当たり前の天皇が東京へ移動しそれに伴い公家や商店で併せて移動してしまいガラッとした京都の街を活気づけようと活躍した企業と思うとその柔軟性と心意気はとても尊敬するものにあります。
本業の仏具は時代の変化に伴い仏具や寺の破壊活動などが起きる廃仏毀釈を経験するなどお先真っ暗感がある中においても理化学機器にシフトしその後は蓄電池で大きく成長を遂げました。
当時の科学技術発展を担った人々は皆、大学卒業などの学歴を持つ中で島津源蔵はまともな学校教育を受けておらずその中でも十大発明家として表彰されます。
これだけ逆境を跳ね除けてさらには地道な活動を支える企業の活躍を見ると時代背景を理由に努力できない自分に少し恥ずかしくも思います。1900年代なんて人類史で最も混乱に揉まれた時代であり、2000年代のように良くも悪くも安定した秩序で生活できる中努力をできないなんて言い訳がましいなと反省します。
それにしても歴史について様々なストーリーを絡めて知れるのはとても面白いことでした。旅行先の歴史を知ることはその土地に立った時に違う感覚を味わう事ができる旅行をより楽しくできる手段に感じます。
